多くの人がエンディングノートの重要性を理解しながらも、実際に書き進めることができずに悩んでいます。2020年の調査によると、エンディングノートを持っている人のうち、実際に書いている人は約60%に過ぎず、全く書いていない人が40%以上という現実があります。また、2024年の調査では、親と終活について話したことがない人が67.7%に上り、エンディングノートを書いている人は全体のわずか13%という状況です。この「書けない」「進まない」現象の背景には、死と向き合うことへの心理的抵抗感、完璧主義によるプレッシャー、項目の多さや専門知識の不足など、様々な要因が複雑に絡み合っています。しかし、適切なアプローチと考え方の転換により、これらの障壁は十分に乗り越えることができます。本記事では、エンディングノートが書けない理由を深掘りし、効果的に書き進めるための具体的な解決策をご紹介します。

Q1. エンディングノートが書けない主な理由は?心理的な障壁を解説
エンディングノートが書けない最大の理由は、心理的な障壁にあります。日本では古くから「死」を直接語ることを避ける文化的風潮が根強く存在し、エンディングノートは「自分の死後」を想定して書く文書であるため、多くの人が心理的な抵抗感を抱いてしまいます。
死への恐怖と文化的タブーが最も大きな要因です。精神科医のフロイトが指摘するように、大病をしない限り、人間は心の奥底で自分は不死だと信じているため、今の人生が永遠に続くという感覚が強く、自身の「最期」を受け入れがたいのです。「自分が死ぬなんて考えたくない」「縁起が悪い」という感情が生まれ、ペンを取ることさえためらってしまいます。
次に、プライバシーや内面をさらけ出すことへの恥ずかしさがあります。エンディングノートには銀行口座や財産状況、介護・医療の希望、さらには家族にも言えない個人的な思いまで、詳細な個人情報を記載する必要があります。「これを書いたら人に見られてしまうのでは?」という不安や、「ここまで自分をさらけ出す必要があるのか」という恥じらいが生じ、筆が止まってしまうのです。
完璧主義によるプレッシャーも大きな障壁となります。市販のエンディングノートは網羅的に項目がまとめられているため、「すべて埋めなければ意味がない」「完璧に仕上げてこそ終活が完了する」という無言のプレッシャーを感じてしまいます。几帳面で真面目な人ほどこの完璧主義に陥りやすく、埋められない項目が出ると挫折の原因となってしまいます。
さらに、自己評価や過去の振り返りへの抵抗も見逃せません。エンディングノートには「自分史」や「思い出」を記入する項目が含まれることが多く、自分の人生を振り返る作業自体が苦痛に感じる人もいます。過去の失敗や後悔に直面したり、自分を客観視することに抵抗を感じたりするため、感謝や思い出を綴ることが心理的に難しいと感じることがあります。
これらの心理的障壁を理解し、まずは「完璧を目指さない」「誰にも見せなくてもいい」という気持ちで始めることが、エンディングノート作成の第一歩となります。
Q2. エンディングノートが進まない実務的な原因と対処法は?
エンディングノートが進まない原因は、心理的な要因だけでなく、実務的・物理的な要因も大きく影響しています。これらの具体的な原因と効果的な対処法を理解することで、書き進める際の障壁を取り除くことができます。
書く習慣がない・面倒くさい・時間がかかるという問題は、多くの人が直面する現実的な課題です。日頃から「書く」ことに慣れていない人にとって、エンディングノートの記入は非常に面倒な作業と感じられます。特に「葬儀やお墓、保険や相続」といった複雑な項目になると、資料を探したり書類を確認したりする作業が発生し、それが億劫になって後回しにしてしまう傾向があります。
対処法としては、デジタルツールの活用が効果的です。エンディングノートアプリやWord、Excelファイルなどを使用すれば、手書きの負担が軽減され、更新や修正も容易になります。また、写真や動画も簡単に記録でき、多くの情報をコンパクトにまとめることができます。
書く内容が多すぎる・項目を埋められない・専門知識の欠如も大きな障壁です。エンディングノートには保険・年金・不動産・税金・医療・介護・葬儀・お墓・相続など、専門家でも難しい内容が多岐にわたります。一般の人がすべての項目を完璧に記入することは困難であり、何から書けばいいのか分からず思考が停止してしまいます。
この問題への対処法は、「情報ハブ」として割り切ることです。最初からすべてを完璧に埋める必要はありません。銀行口座や保険の一覧、重要書類の保管場所、スマートフォンやパソコンのパスワードなど、家族が困らない最低限の情報から書き始めることが重要です。ノートのページが虫食い状態になっても全く問題なく、全体の2割しか埋まっていなくても、その価値は絶大です。
情報が流動的で書けないという問題は、特に若い世代や現役世代に多く見られます。財産や交友関係がまだ変化する可能性が高いため、「何十年後も一緒なのだろうか?」といった疑問が生じ、書き進める手が止まってしまいます。
この場合は、定期的な見直しと更新を前提とすることで解決できます。1~3ヵ月に一度大まかな内容を確認し、3~6ヵ月に一度はより詳細な見直しを行うことで、常に最新の状態を保つことができます。
高齢者特有の身体的困難(手の痛みや震えなど)については、代筆や聞き書き形式を活用しましょう。家族や専門家に代筆してもらい、口頭で内容を述べてそれを書き留める方法が有効です。ただし、代筆の場合は誰が代筆したか、どういう経緯で代筆したかを明示し、可能であれば自筆で署名・捺印することが推奨されます。
Q3. エンディングノートを書き始めるための具体的なコツと手順は?
エンディングノートを効果的に書き始めるためには、段階的なアプローチと具体的なコツを活用することが重要です。一度に完成させようとせず、書きやすい項目から少しずつ進めることで、無理なく継続できます。
ステップ1:書きやすい項目から始める
まずは事実ベースの簡単な情報から書き始めましょう。氏名、生年月日、現住所、血液型などの基本的なプロフィール情報や、親しい友人の連絡先など、感情的な負担が少ない項目から取り組むことで、スムーズに筆を進めることができます。
次に、「これだけはやってほしいことリスト」を作成することをおすすめします。突然動けなくなった場合に家族が困らないよう、日々の生活に関するお金関係(新聞代、光熱費、サブスクリプション契約など)、連絡先、利用サービスの停止方法などを書き出します。これらは比較的書きやすく、かつ実用性が高い情報です。
ステップ2:財産情報の基本を整理する
銀行口座、生命保険、不動産、有価証券など、所有する財産の基本情報を記録します。ただし、最初から詳細を完璧に書く必要はありません。銀行名、支店名、口座種別だけでも十分価値があります。暗証番号などのセキュリティ情報は直接記載せず、ヒントを記したり、別途管理している場所を示したりする工夫をしましょう。
現代では、PayPayや楽天Edyなどの電子マネー、仮想通貨、NFTといったデジタル資産も重要です。これらのアカウント情報やウォレット情報も忘れずに記載しておきましょう。
ステップ3:医療・介護の希望を考える
現在の健康状態、かかりつけ医、持病、常用薬、アレルギーなどの医療情報を整理します。特に重要なのが終末期の医療・延命治療に関する意思です。病名告知や余命告知を望むか、延命治療を希望するか否かなど、家族が難しい決断を迫られた際に本人の意思を尊重できるよう、具体的に記しておきます。
ステップ4:家族との対話のきっかけにする
一人で悩んで書けない項目がある場合は、思い切って家族に相談することが効果的です。エンディングノートを「対話のきっかけ(コミュニケーションツール)」として活用し、介護や延命治療、お墓のことなど、重いテーマを家族と一緒に考える時間を持ちましょう。「正直どうしたらいいか迷っていて。あなたはどう思う?」と切り出すことで、書面だけでは伝わらない本当の意味での安心を遺すことができます。
ステップ5:定期的な見直しと更新
エンディングノートは一度書いたら終わりではありません。時間の経過とともに記載内容の修正や追加が必要になるため、定期的な見直しと更新が不可欠です。1~3ヵ月に一度、大まかな内容を確認し、3~6ヵ月に一度はより詳細な見直しを行うことで、常に最新で実用的な状態を保つことができます。
これらのステップを踏むことで、エンディングノートを無理なく、着実に書き進めることができるでしょう。
Q4. エンディングノートの項目が多すぎて挫折しそう。どこから書けばいい?
エンディングノートの項目の多さに圧倒されて挫折してしまうのは、多くの人が経験する共通の悩みです。しかし、優先順位を明確にし、段階的に取り組むことで、この問題は効果的に解決できます。
最優先項目:緊急時に必要な基本情報
まず最初に書くべきは、緊急時に家族が必要とする基本的な情報です。氏名、生年月日、現住所、本籍地、血液型、健康保険証の情報、かかりつけ医、持病、常用薬、アレルギーなどの医療情報を優先的に記載しましょう。これらの情報は、病気や事故などの緊急事態で本人が意識を失った場合に、医療機関や救急隊が適切な処置を行うために不可欠です。
第2優先:日常生活の継続に必要な情報
次に重要なのは、家族が日常生活を継続するために必要な情報です。光熱費、新聞代、携帯電話料金などの固定費の支払い方法、銀行口座の基本情報(銀行名、支店名、口座種別)、クレジットカードやサブスクリプションサービスの契約情報、SNSアカウントの存在などを記載します。これにより、突然の状況変化でも家族が混乱することなく、必要な手続きを進めることができます。
第3優先:財産関連の基本情報
財産情報は詳細を完璧に書く必要はありません。「家族のための情報ハブ(拠点)」として割り切り、生命保険の契約内容と証券の保管場所、不動産の所在地と関連書類の保管場所、有価証券の証券会社名と口座情報の概要など、家族が詳細を調べるための手がかりとなる情報を中心に記載しましょう。
現代では電子マネーや仮想通貨などのデジタル資産も重要です。PayPay、楽天Edy、ビットコインなどのアカウント情報も忘れずに記載しておきます。ただし、パスワードは直接書かず、ヒントを記したり別途管理している場所を示したりする工夫が必要です。
第4優先:医療・介護・葬儀の希望
自身の価値観や希望を反映させたい分野として、終末期医療や延命治療に関する意思、介護サービスの希望、葬儀の形式や規模、お墓や納骨の希望などを記載します。これらは家族が重要な決断を迫られた際に、本人の意思を尊重するために役立ちます。
最後に:感謝のメッセージと思い出
時間と気持ちに余裕ができたら、家族や友人への感謝のメッセージや自分史、これからやりたいことなどを記載します。これらは必須項目ではありませんが、遺族にとって大きな心の支えとなる貴重な内容です。
効率的な書き方のコツ
項目を埋める際は、箇条書きや簡潔なメモ形式で構いません。文章の体裁を気にする必要はなく、鉛筆で書いて後から修正しても全く問題ありません。また、「分からない」「後で調べる」と書いておくことで、完璧主義によるプレッシャーを回避できます。
全体の2割程度しか埋まっていなくても、それだけで家族にとって非常に価値のある情報となることを忘れずに、気軽に取り組むことが継続の秘訣です。
Q5. エンディングノートを完成させるためのモチベーション維持方法は?
エンディングノートを完成させるためには、長期的なモチベーション維持が不可欠です。一度に完成させようとせず、継続可能なアプローチと心構えを持つことで、無理なく書き進めることができます。
考え方の根本的な転換
まず最も重要なのは、エンディングノートに対する考え方を転換することです。「死の準備」ではなく「今をより良く生きるためのツール」として捉えることで、ネガティブな感情を軽減できます。エンディングノートを書く行為は、自分の価値観や大切なものを見つめ直し、自己表現やセルフケアの一環として機能します。この視点の転換により、書くこと自体が前向きな活動となり、モチベーションの維持につながります。
「完璧を目指さない」という割り切り
エンディングノートは「情報ハブ(拠点)」として機能すれば十分です。すべての項目を完璧に埋める必要はなく、家族が困らない最低限の情報があれば価値は絶大です。「この1冊で完璧」という幻想がプレッシャーの原因であることを理解し、むしろ断片的でも有用な情報を残すことに焦点を当てましょう。
段階的な目標設定と達成感の積み重ね
大きな目標を小さなステップに分割し、達成感を積み重ねることがモチベーション維持の鍵です。「今週は基本情報だけ」「来週は銀行口座の一覧」といった具合に、無理のない小さな目標を設定し、それを達成するたびに自分を褒めることで、継続する意欲を保つことができます。
デジタルツールの活用による負担軽減
手書きが負担に感じる場合は、エンディングノートアプリやWord、Excelファイルなどのデジタルツールを積極的に活用しましょう。デジタル版は更新や修正が容易で、写真や動画も簡単に記録できるため、多くの情報をコンパクトにまとめられます。また、パスワード管理により、家族や周囲の目を気にせず少しずつ書き足すことが可能です。
家族やコミュニティとの共有
一人で悩まず、家族と相談しながら書くことで、孤独感を軽減し、継続する動機を得ることができます。また、地域のコミュニティセンターやカルチャースクールで開催される「エンディングノート講座」や「終活ワークショップ」に参加することで、同じ悩みを持つ人同士が情報を共有し、モチベーションを維持しやすくなります。
定期的な見直しによる継続感
エンディングノートは一度書いたら終わりではなく、定期的な見直しと更新が必要です。1~3ヵ月に一度の見直しを習慣化することで、継続的に取り組んでいる実感を得ることができ、長期的なモチベーション維持につながります。
サポートサービスの活用
完全無料・予約不要でエンディングノートの執筆サポートを提供するサービスも存在します。終活のプロが常駐し、書き方のアドバイスや支援を受けられるため、一人では続かない場合の心強いサポートとなります。
「今」の充実を意識する
エンディングノートには「これからの計画・やりたいこと」を記載する項目もあります。死後の準備だけでなく、残りの人生をどのように充実させるかを考える機会として活用することで、前向きな気持ちで取り組むことができ、自然とモチベーションが維持されます。
これらの方法を組み合わせることで、エンディングノートの作成を継続し、最終的に家族にとって価値のある情報を残すことができるでしょう。




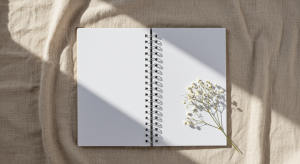



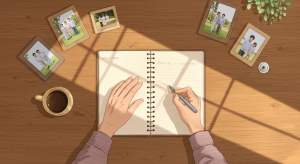
コメント