超高齢社会を迎えた日本では、認知症は誰もが直面する可能性のある課題となっています。2024年時点で認知症患者数は471万人と推計され、約5.4人に1人が認知症になる可能性があると言われています。令和6年1月には「認知症基本法」が施行され、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会の実現が目指されています。このような状況の中で、判断能力が低下する前の備えが極めて重要になってきます。エンディングノートは、自身の意思を明確にし、家族の負担を軽減するための重要なツールとして注目されています。認知症への備えは決して高齢者だけの問題ではありません。すべての世代が将来への備えを行うことで、個人と家族の安心につながるのです。
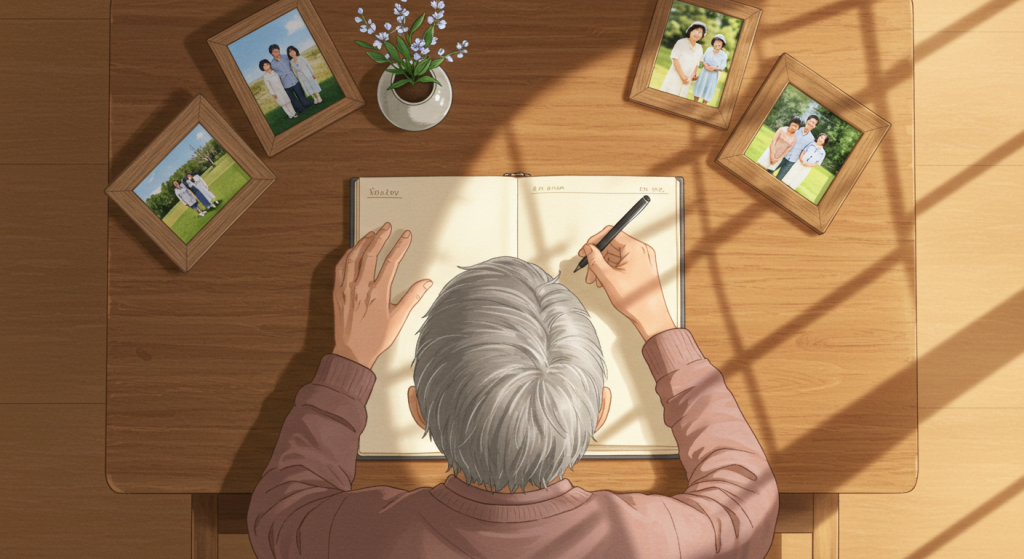
Q1: エンディングノートは認知症への備えとして本当に効果があるのですか?
エンディングノートは、認知症への備えとして非常に効果的なツールです。遺言書とは異なり法的拘束力はありませんが、自由に思いや意向を記録することができ、本人が意思の疎通が困難になった場合の重要な指針となります。
認知症になると適切な判断ができなくなるため、様々な問題が生じます。特に深刻なのが財産管理の問題です。口座の名義人が認知症だとわかると、銀行は口座を凍結します。これは認知力が低下した名義人が犯罪や詐欺に巻き込まれて資産を失うのを防ぐための措置ですが、家族であっても簡単に預金を引き出すことができなくなってしまいます。
エンディングノートを作成することで、認知症の介護にかかる家族の負担を直接的に減らせるわけではありませんが、情報の整理と意思の明確化により、家族の手間を大幅に減らすことができます。例えば、銀行口座の情報や利用しているサービスのID・パスワードを記録しておくことで、家族がこうした情報を探したり問い合わせたりする必要がなくなります。
また、家族が延命治療などについて困難な決断を迫られた際、本人の意思を確認できない状況は大きな心理的負担となります。しかし、自分の考えや希望をエンディングノートに書き留めておくことで、家族に間接的に意思を伝えることができ、家族の心理的負担を軽減することが可能です。物事を書き留めることは考えをまとめることに役立ち、判断能力を失った時に家族が参考にする重要な指針となるのです。
Q2: 判断能力が低下する前にエンディングノートに何を書けばよいですか?
エンディングノートには決まった形式がないため、「自分が思うこと」「伝えたい情報」を自由に書くことができますが、認知症への備えとして特に重要な項目があります。
最優先で記載すべき基本情報として、氏名、生年月日、出生地、本籍地などの基本情報を正確に記載し、緊急時に連絡すべき人の情報も必須です。これらの情報が整理されていることで、家族が各種手続きを行う際の負担が大幅に軽減されます。
金融・資産情報は本人と家族の双方が把握しておかなければならない重要な項目です。銀行口座と金融資産、有価証券や投資信託、不動産の保有状況、生命保険の詳細を記録します。特にオンラインバンキングの口座やクレジットカードについては、パスワードを直接書くのではなく、家族だけが理解できるコードや文言を使用することが推奨されます。
医療・介護に関する希望も重要な項目です。病歴とアレルギー情報、現在服用中の薬物、希望する医療処置、終末期ケアの希望、臓器提供に関する意向を含めます。介護や医療についての希望、最期の迎え方について書くことは、自分の気持ちを見つめ直す良い機会にもなります。
介護・支援に関する意向では、誰に介護を頼みたいか(配偶者、介護ヘルパー、子供など)、介護を受ける場所の希望(施設または在宅介護)を記載します。施設を希望する場合は、希望する介護施設の名称も記録しておくとよいでしょう。
遺言書のような決まった規則がないため、気軽に作成でき、何か思いついたときに内容を追加・修正できます。特に資産状況は年々変化するため、定期的な見直しが重要です。
Q3: 認知症になると銀行口座が凍結されるって本当ですか?その対策は?
はい、これは事実です。口座の名義人が認知症だとわかると、銀行は口座を凍結します。これは認知力が低下した名義人が犯罪や詐欺に巻き込まれて資産を失うのを防ぐための措置ですが、このような状況になると、家族であっても簡単に預金を引き出すことができなくなります。
高齢者世帯において、家族が最も困るのがこの財産管理の問題です。認知症を発症した場合、資産があっても住宅改修や介護施設費用のための資金を自由に使用することができなくなります。一部のケースでは500万円以上の費用が必要になることもあり、事前の準備がない場合は深刻な問題となります。
対策として最も重要なのは事前の準備です。まず、エンディングノートに銀行口座の情報を整理して記載し、家族がアクセスできるようにしておきます。ただし、オンラインバンキングのパスワードなどは直接記載せず、家族だけが理解できるコードや文言を使用することが安全です。
法的な対策としては、成年後見制度の活用があります。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがありますが、任意後見制度は判断能力があるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。
また、家族信託という選択肢もあります。これは家族間で財産管理を委託する仕組みで、より柔軟な資産管理が可能になります。家族信託では金融機関によって対応は異なりますが、余剰資金による不動産の購入や投資をすることも可能で、原則として裁判所の関与がなく、判断能力があるうちから契約を締結し、即時に財産管理を開始できる制度です。
2024年現在の成年後見制度の利用状況を見ると、認知症の高齢者数は443.2万人と推計されていますが、成年後見の利用者は2023年末時点で計約25万人、わずか5%程度の利用にとどまっています。これは多くの人が制度を知らないか、利用に踏み切れていないことを示しており、早期の情報収集と準備が重要です。
Q4: エンディングノートと成年後見制度や家族信託はどう使い分けるべきですか?
エンディングノートと各制度はそれぞれ異なる役割を持っており、組み合わせることでより包括的な備えが可能になります。
任意後見制度は、判断能力の低下に備えて、財産管理や身上監護に関して受任者へ代理権を与えておく制度です。メリットとして、財産管理と身上監護の両方について定められ、本人が信頼のおける人物を任意後見人に選任でき、支援内容や形態に本人の希望を反映できます。また、任意後見人が医療機関や介護施設への入所手続きを代行することが可能です。デメリットは、家庭裁判所の監督があるため、積極的な資産運用や大きな財産処分には制限がかかる場合が多いことです。費用面では、任意後見人が家族や親族の場合は無報酬から月額5万円、専門家の場合は月額2から6万円となります。
家族信託は、財産管理を家族に託して資産凍結を防ぐことを主な目的とした制度です。メリットとして、金融機関によって対応は異なりますが、余剰資金による不動産の購入や投資をすることも可能で、原則として裁判所の関与がありません。また、判断能力があるうちから契約を締結し、即時に財産管理を開始できる制度です。デメリットは、財産に関する対策を行う制度なので、本人の日常生活や医療・介護に関する契約や手続きを代理する「身上監護」については定められないことです。費用は50から100万円程度かかる場合が多くなります。
使い分けの指針として、両制度の主な違いを理解することが重要です。財産管理の柔軟性では家族信託が優れており、本人が信頼できる人を受託者として選び、契約で定めた範囲内で自由度の高い財産管理を任せることができます。身上監護の対応では任意後見制度が必要で、家族信託は財産管理のみを対象とするため身上監護については対応しません。効力の発生時期では、家族信託は判断能力があるうちから即時に財産管理を開始できますが、任意後見制度の効力発生は判断能力低下後となります。
理想的なのは併用です。家族信託と任意後見制度は併用することができ、お互いのデメリットを補うことができます。財産管理については家族信託で柔軟な対応を図り、身上監護については任意後見制度でカバーするといった使い分けが可能です。
エンディングノートの役割は、これらの制度についての意向を記載し、家族に自分の考えを伝えることです。また、制度だけではカバーできない細かな希望や価値観を記録する重要なツールとして機能します。
Q5: 認知症の初期症状を見逃さないためのチェックポイントと予防法は?
認知症の早期発見は症状の悪化を遅らせるために極めて重要です。MCI(軽度認知障害)を放置すると、その中の約1割の方は1年以内に認知症を発症すると言われています。しかし、MCI段階で適切な治療を施すことができれば、健常な認知機能まで回復する可能性が14から44%もあるとされています。
認知症の初期症状チェックリストとして、以下の5つの症状がみられることが多くなります。記憶障害(もの忘れ)では何度も同じことを聞く、同じものを買うといった症状があります。見当識障害では今日の日付や通り慣れた道がわからなくなります。理解力・判断力の低下ではテレビの内容が理解できなくなります。実行機能障害では料理の味付けが変化する、家電の使い方を忘れるといった症状が現れます。性格の変化では怒りっぽくなる、ふさぎ込んで何事もおっくうになるといった変化が見られます。
より具体的なチェック項目として、今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる、同じことを何度も言う・問う・する、しまい忘れ置き忘れが増えいつも探し物をしている、財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う、料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなったといった症状があります。
予防・対策方法では複数のアプローチが効果的です。有酸素運動は脳への血流を増やすため認知症の予防・対策に効果的です。散歩や水泳のような身体への負担が少ない運動を選んで取り組むのがおすすめです。認知トレーニングとして、脳トレやパズル、計算ドリルといった認知トレーニングに取り組むのも効果的です。脳への刺激を増やすことで脳細胞を活性化し、認知機能の維持につながります。
生活習慣の改善も重要です。生活習慣病は脳卒中を引き起こす動脈硬化のリスクを高めるといわれています。認知症を予防するためには、生活習慣病を適切に治療することが重要です。栄養バランスの取れた食事は脳の機能を維持し、認知症のリスクを低減するのに役立ちます。また、質の良い睡眠は「アルツハイマー型認知症」の原因物質である「アミロイドβ」を脳から血液中に排出し、肝臓で分解するため、認知症予防には欠かせません。
対応方法として、上記のチェックリストで認知症の初期症状が疑われる場合は、まず、かかりつけ医や認知症専門の医療機関に相談し、診断を受けることが重要です。「認知症かも?」と思われる言動があった際にはなるべく早めに専門医の診察を受けるようにしてください。ただし、チェックリストはあくまで目安であり、認知症を診断するものではありません。心配な場合は医師に相談することが基本です。
エンディングノートの作成と合わせて、これらの予防対策と早期発見の取り組みを行うことで、認知症への包括的な備えが可能になります。
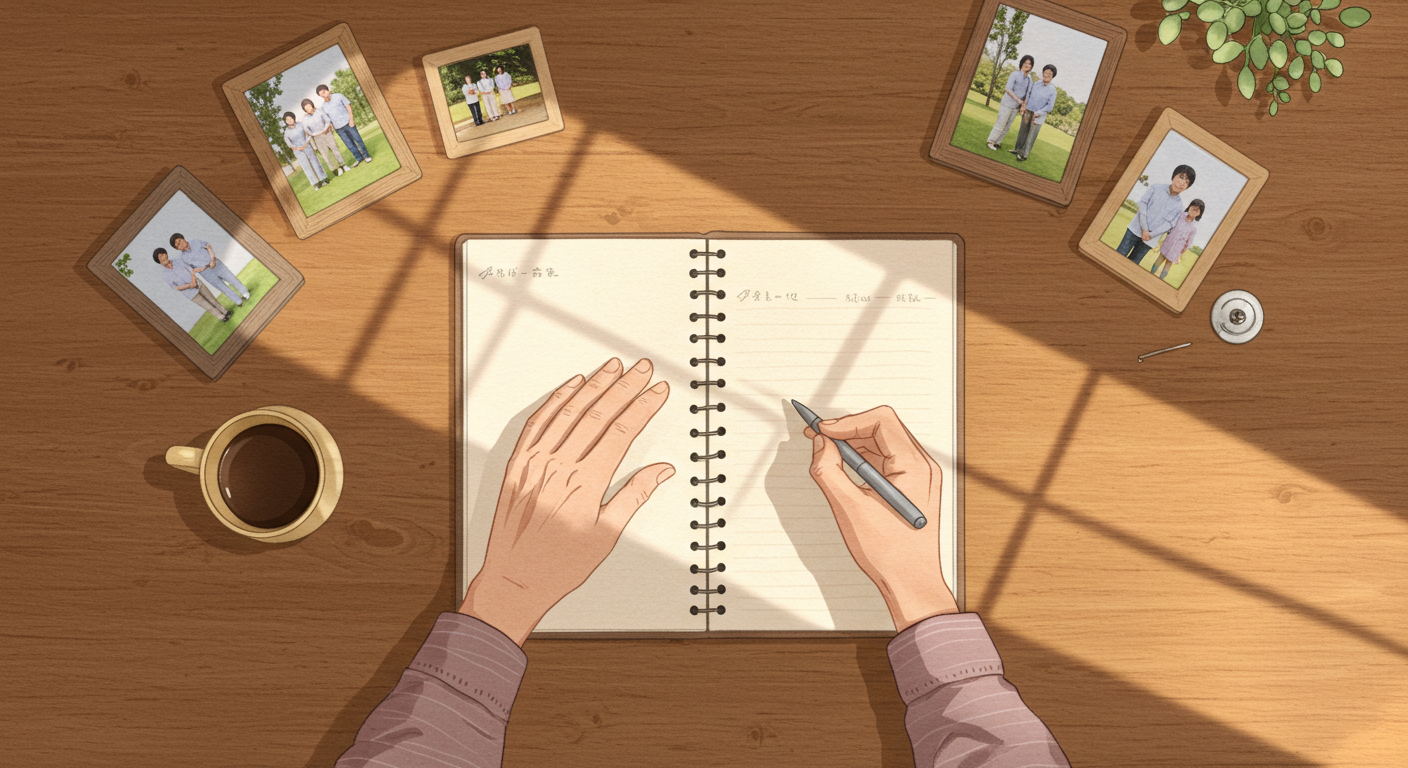








コメント