2025年10月1日、日本の相続制度において画期的な変革が実現しました。公正証書遺言の作成手続きがデジタル化され、従来は公証役場への出向が必須だった遺言作成が、オンラインでも可能となったのです。この変更は、2023年6月14日に公布された「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づくもので、高齢化が進む日本社会において、より多くの方が遺言を作成しやすくなることを目指しています。特に、高齢で外出が困難な方や、地方在住で公証役場が遠方にある方にとって、このデジタル化は大きなメリットをもたらす制度改正となりました。本記事では、すでに施行された公正証書遺言のデジタル化について、具体的な変更点や新しい手続きの流れ、費用、注意すべきポイントなどを詳しく解説していきます。
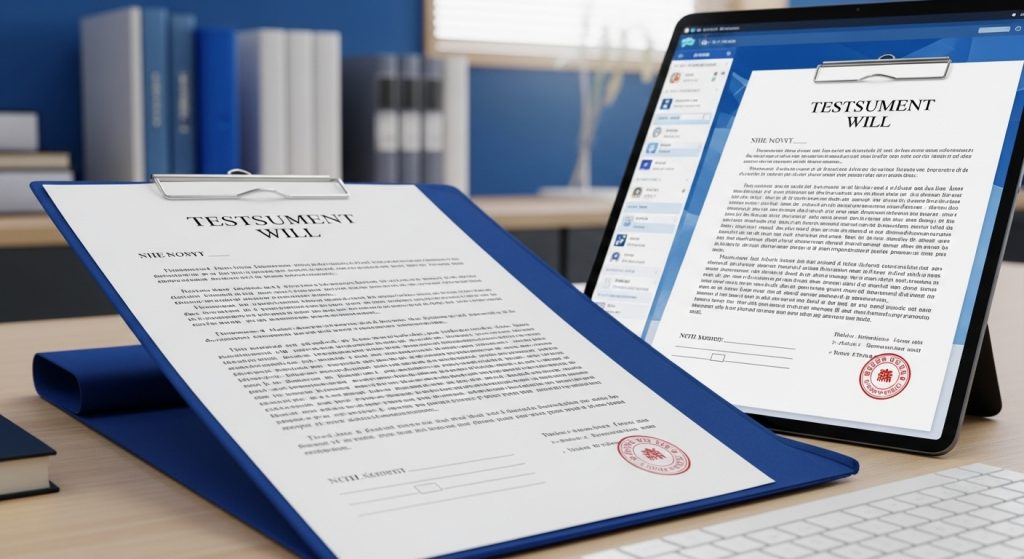
公正証書遺言のデジタル化を実現した法律とその背景
公正証書遺言のデジタル化を可能にしたのは、令和5年法律第53号として公布された「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」です。この法律は、民事関係の各種手続きにおいて情報通信技術を積極的に活用し、国民の利便性を向上させるとともに、手続きの効率化を図ることを大きな目的としています。
法律の公布から約2年4ヶ月を経て、2025年10月1日に公正証書のデジタル化に関する規定が施行されました。この法律により、公正証書全般について三つの重要な変更が実現しています。第一に、インターネットを利用した電子署名による公正証書の作成申請が可能になったこと、第二に、公証人が相当と認める場合にはウェブ会議を利用した方法で公正証書を作成できるようになったこと、第三に、公正証書の原本を電子データで作成し保存することが原則となり、正本や謄本も電子データでの交付が可能になったことです。
この制度改正の背景には、日本社会の急速な高齢化があります。相続に関する需要は年々増加していますが、従来の公正証書遺言作成には、遺言者が必ず公証役場に出向かなければならないという大きな課題がありました。高齢で体が不自由な方や、入院中の方、介護施設に入居されている方にとって、公証役場への移動は大きな負担となっていたのです。また、地方では公証役場の数が少なく、最寄りの公証役場まで何時間もかかるケースも珍しくありませんでした。
さらに、紙の書類で作成・保管される従来の方式では、正本や謄本の管理が煩雑であり、紛失や劣化のリスクも避けられませんでした。デジタル化が進む現代社会において、行政手続きの効率化と利便性向上は急務とされており、こうした複合的な課題を解決するために、法務省は公正証書作成手続きのデジタル化を推進してきました。
公正証書遺言とは何か
公正証書遺言について改めて説明しますと、これは公証人が遺言者の口述に基づいて作成する遺言書のことを指します。公証人とは、裁判官や検察官などを長年務めた法律の専門家で、国から任命された公務員です。公証人が作成に関わることで、遺言の内容が法的に適切であることが担保され、遺言の方式の中でも最も確実性が高く、無効になるリスクが低いとされています。
従来の公正証書遺言作成では、遺言者本人が公証役場に出向き、2人以上の証人の立会いのもとで、公証人に遺言の内容を口述する必要がありました。公証人はその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、全員が署名・押印することで公正証書遺言が完成するという流れでした。この厳格な手続きにより、遺言の真正性と有効性が確保されてきたのですが、同時に遺言者にとっては手続きのハードルが高いという側面もありました。
2025年10月から実施された主要な変更点
2025年10月1日から施行された公正証書遺言のデジタル化には、四つの重要な変更点があります。
オンライン面談の実現
最も大きな変更は、オンライン会議システムを利用した面談が認められるようになったことです。これまで遺言者は必ず公証役場に足を運び、公証人と直接対面で面談する必要がありましたが、デジタル化後は、ビデオ通話を通じて遺言内容を口述できるようになりました。
遺言者は自宅や入居している施設など、自分が希望する場所からオンラインで公証人と面談し、遺言を作成することができます。これにより、公証役場が遠方にある方や、身体的な理由で外出が困難な高齢者、入院中の方でも、容易に公正証書遺言を作成できるようになりました。
ただし、オンライン面談には一定の要件があります。遺言者の意思確認や本人確認を適切に行うため、十分な画質や音質が確保された環境が必要です。また、デジタル機器の操作に不慣れな遺言者の場合は、家族や専門家のサポートが必要になることもあります。公証人は、オンライン面談を通じて遺言者の意思能力を確認し、遺言内容が遺言者の真意に基づくものであることを慎重に見極めます。
電子署名の採用
従来の公正証書遺言では、遺言者と証人が紙の書類に署名し、実印を押印する必要がありました。デジタル化後は、この署名・押印に代わり、電子署名が認められるようになっています。
電子署名の具体的な方法としては、公証人のパソコンの画面、または公証人のパソコンに接続されたペンタブレットに、タッチペンで氏名を記載し、これを公正証書原本の所定の部分に画像として記録する方式が採用されています。この方式により、実印や印鑑証明書の準備が不要になり、手続きの簡素化が実現しました。
ただし、電子署名には一定のセキュリティ対策が施されており、本人確認も厳格化されています。電子署名のデータは暗号化技術により保護され、改ざんを防ぐための措置が講じられています。この技術的な保護により、紙の書類に押印する場合と同等以上の信頼性が確保されているのです。
電子データでの作成と保管
公正証書遺言は、原則としてPDF形式の電子データで作成され、保存されることになりました。公証役場では、この電子データが原本として厳重に管理されます。電子データは複数の場所にバックアップされ、災害などによる滅失のリスクを最小限に抑える体制が整えられています。
遺言者に交付される正本や、将来相続手続きで必要になる謄本についても、電子データで受け取ることができます。もちろん、希望すれば従来通り紙の書類として発行してもらうことも可能です。遺言者は、自分の状況や希望に応じて、電子データか紙の書類かを選択できるようになっています。
電子データでの保管には多くのメリットがあります。紙の書類のように経年劣化することがなく、長期間にわたって鮮明な状態で保管できます。また、紛失や火災などによる滅失のリスクも大幅に低減されます。必要なときにすぐにアクセスでき、複製も容易です。相続人も電子データで謄本を取得できるため、相続手続きの迅速化が期待されています。
本人確認方法の変化
デジタル化に伴い、本人確認の方法にも変化が生じました。従来は実印と印鑑証明書による本人確認が一般的でしたが、デジタル化後は、マイナンバーカードを用いたeKYC(オンライン本人確認)が主流になっています。
eKYCとは「electronic Know Your Customer」の略で、顔認証技術などを用いたオンライン上での本人確認システムです。遺言者はビデオ通話でマイナンバーカードを提示し、カードに記載された顔写真と実際の顔を照合することで、本人確認が行われます。この方式により、印鑑証明書などの書類を事前に市区町村役場で取得する手間が省けるようになりました。
ただし、マイナンバーカードを持っていない方は、事前に取得する必要があります。また、公証役場によっては、運転免許証やパスポートなど、他の顔写真付き身分証明書での確認も可能な場合があります。具体的な運用方法は公証役場ごとに異なる可能性があるため、事前に確認することをお勧めします。
デジタル化された公正証書遺言の作成手続きの流れ
デジタル化後の公正証書遺言作成は、以下のような流れで進められます。
専門家への事前相談
遺言書の内容については、作成前に弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、相続財産に不動産や非上場株式が含まれる場合や、相続人が複数いて相続分の配分が複雑な場合、相続人間でトラブルが予想される場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
専門家への相談は、従来通りオンラインや電話、対面での打ち合わせなど、様々な方法で行えます。専門家と十分に相談しながら、遺言の内容を固めていくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。遺留分への配慮や、特定の相続人への配慮など、法律的な観点からのアドバイスを受けることができるのです。
公証人への連絡と日程調整
遺言の内容が固まったら、公証役場に連絡し、公正証書遺言作成の意向を伝えます。この際、オンラインでの作成を希望するか、従来通り公証役場に出向いて作成するかを選択できます。
オンラインでの作成を希望する場合は、ビデオ通話が可能な環境を用意する必要があります。具体的には、パソコンやタブレット端末、安定したインターネット接続、カメラとマイクが必要です。スマートフォンでも可能な場合がありますが、画面が小さいため、タブレットやパソコンの方が推奨されます。これらの準備が整ったら、公証人と面談の日時を調整します。
遺言原案の作成と確認
事前に、遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言の原案を作成します。この段階では、メールや郵送、FAXなどでやり取りが行われることが多いです。デジタル化後も、この部分の流れは大きく変わっていません。
遺言者は公証人が作成した原案を確認し、修正が必要な場合は公証人に伝えます。何度か修正を重ねて、最終的な遺言内容を確定していきます。この過程で、法律的に問題がないか、遺言者の意図が正確に反映されているかを丁寧にチェックすることが大切です。
証人の手配
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。これはデジタル化後も変わりません。証人には一定の要件があり、成年であること(18歳以上)、推定相続人や受遺者、その配偶者、直系血族でないこと、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、雇人でないことが求められます。
証人は、遺言者自身が知人に依頼することもできますが、専門家に依頼することも可能です。弁護士や司法書士、行政書士などが証人を務めることもあります。また、公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。証人を依頼する場合は、1人あたり5,000円から15,000円程度の日当を支払うのが一般的です。
デジタル化後の大きな変化として、証人もオンラインで立ち会うことが可能になりました。証人は遺言者と同じ場所にいる必要はなく、それぞれ別の場所からオンラインで参加することもできます。これにより、証人の日程調整が容易になり、地理的な制約も大幅に緩和されました。
オンライン本人確認の実施
面談の前に、オンラインでの本人確認が行われます。遺言者はビデオ通話でマイナンバーカードを提示し、公証人が顔認証技術を用いて本人確認を行います。このeKYCのプロセスでは、マイナンバーカードに記載された顔写真と、ビデオ通話に映っている遺言者の顔を照合し、本人であることを確認します。
マイナンバーカードがない場合は、運転免許証やパスポートなど、顔写真付きの身分証明書での確認も可能な場合があります。ただし、具体的な運用方法は公証役場によって異なる可能性があるため、事前に確認が必要です。本人確認は遺言の有効性を担保する重要なプロセスであり、慎重に行われます。
オンライン面談と遺言内容の口述
予定された日時に、オンライン会議システムを用いて面談が行われます。遺言者、公証人、2人以上の証人が、ビデオ通話で接続します。複数の参加者が同時に画面に表示され、全員が互いの顔を確認できる状態で手続きが進められます。
公証人は、まず遺言者の本人確認と意思能力の確認を行います。遺言者が自由な意思で遺言を作成しようとしているか、遺言の内容を理解する能力があるかを慎重に見極めます。その後、遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。公証人はその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者と証人は、その内容が正確であることを確認します。
この過程で、公証人は遺言の内容について法律的な観点から助言することもあります。遺言の内容が法律に違反していないか、遺言者の意図が正確に表現されているかを確認しながら、手続きが進められるのです。
電子署名の実施
内容に間違いがなければ、電子署名を行います。公証人のパソコンに接続されたペンタブレットや、画面上で、遺言者と証人がタッチペンで氏名を記載します。この署名は画像データとして公正証書原本に記録されます。実印を押す代わりに、電子的な方法で署名を行うことで、手続きが完結します。
電子署名のデータには、署名した日時や場所などの情報も記録され、後から改ざんできないように技術的な保護が施されています。この仕組みにより、紙の書類に実印を押印する場合と同等以上の信頼性が確保されているのです。
電子データでの保管と交付
公正証書遺言は、PDF形式の電子データとして公証役場のシステムに保管されます。遺言者には、正本が電子データまたは紙の書類として交付されます。電子データでの交付を希望する場合は、メールやクラウドストレージを通じて受け取ることができます。紙の書類を希望する場合は、郵送または公証役場での受け取りが可能です。
公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管され、相続が発生した際には、相続人が謄本を取得できます。電子データで保管されているため、経年劣化や災害による滅失のリスクが大幅に低減されています。
公正証書遺言の保管と管理
作成された公正証書遺言の正本は、遺言者自身が保管します。紙の正本を受け取った場合は、自宅の金庫や銀行の貸金庫など、安全な場所に保管します。電子データの場合は、パソコンやクラウドストレージに保管しますが、パスワードなどのセキュリティ対策を忘れずに行う必要があります。
また、遺言の存在を相続人に知らせておくことも重要です。遺言があることを知らなければ、相続人が遺言を見つけられず、遺言の内容が実現されない可能性があります。信頼できる家族や、遺言作成をサポートした専門家に、遺言の存在と保管場所を伝えておくとよいでしょう。
デジタル化がもたらすメリット
公正証書遺言のデジタル化には、多くのメリットがあります。
アクセシビリティの飛躍的な向上
最大のメリットは、公証役場に出向く必要がなくなることです。高齢者や身体が不自由な方、地方在住で公証役場が遠方にある方でも、自宅から遺言を作成できるようになりました。特に、入院中や介護施設に入居している方にとって、この変更は画期的です。
従来は、体調が悪化する前に無理をして公証役場に出向く必要がありましたが、デジタル化後は、体調や状況に応じて柔軟に遺言作成のタイミングを選べるようになりました。これにより、遺言作成のハードルが大きく下がり、より多くの人が遺言を残せるようになっています。
時間と費用の大幅な節約
公証役場への往復にかかる時間や交通費が不要になります。特に遠方の方にとっては、大きな負担軽減になります。従来は、公証役場までの往復に半日や1日を費やすこともありましたが、オンラインであれば、面談の時間だけで済みます。
また、証人もオンラインで立ち会えるため、証人の日程調整がしやすくなりました。証人を依頼する際の交通費なども節約できます。証人が遠方に住んでいる場合でも、オンラインで参加してもらえるため、地理的な制約がなくなりました。
安全で確実な保管と管理
電子データで保管されるため、紙の書類のように紛失や劣化、火災などによる滅失のリスクがありません。公証役場のシステムで厳重に管理され、複数の場所にバックアップされているため、長期間安全に保管されます。
必要なときにすぐにアクセスでき、複製も容易です。相続が発生した際、相続人が謄本を取得する手続きも簡素化されます。遠方に住んでいる相続人でも、オンラインで謄本を取得できるため、相続手続きがスムーズに進むようになりました。
手続きの簡素化と効率化
実印や印鑑証明書の準備が不要になり、マイナンバーカードでの本人確認が可能になりました。これにより、事前に市区町村役場に出向いて印鑑証明書を取得する手間が省けます。電子署名により、押印の手間もなくなります。全体として、手続きがスムーズに進むようになっています。
書類のやり取りも電子化されるため、郵送を待つ時間も短縮されます。従来は原案の確認や修正に時間がかかることもありましたが、メールでのやり取りにより、迅速に対応できるようになりました。
環境への配慮
紙の使用量が減ることで、環境負荷の軽減にもつながります。従来は、公正証書遺言の作成に多くの紙が使用されていましたが、電子化により、紙の消費が大幅に削減されます。持続可能な社会の実現に向けて、小さいながらも確実な貢献となっています。
デジタル化のデメリットと注意点
メリットが多い一方で、デジタル化にはいくつかのデメリットや注意点もあります。
デジタル機器への不慣れという課題
高齢者の中には、パソコンやタブレット、オンライン会議システムの操作に不慣れな方も多くいます。デジタル機器の扱いに不安がある場合、オンラインでの遺言作成がかえってハードルになる可能性があります。
このような場合は、家族や専門家のサポートを受けるか、従来通り公証役場に出向いて作成する方法を選択することもできます。デジタル化は選択肢を増やすものであり、従来の方法も引き続き利用可能です。
安定したインターネット環境の必要性
オンラインでの作成には、安定したインターネット接続が必要です。通信環境が悪いと、面談が中断したり、本人確認がうまくできなかったりする可能性があります。特に地方では、インターネット環境が整っていない地域もあります。
事前にインターネット接続を確認し、必要に応じて環境を整える必要があります。Wi-Fi環境が不安定な場合は、有線LANでの接続を検討するなど、安定した通信環境を確保することが重要です。
セキュリティリスクへの対応
電子データでの保管には、セキュリティ対策が重要です。パスワードの管理が不十分だと、第三者にアクセスされるリスクがあります。また、電子データの保管場所を相続人に伝えていないと、遺言の存在が見つからない可能性もあります。
適切な管理と情報共有が必要です。パスワードは複雑なものを設定し、定期的に変更することが推奨されます。また、電子データの保管場所やアクセス方法を、信頼できる家族や専門家に伝えておくことが重要です。
すべての公証役場での対応状況
デジタル化は2025年10月1日から開始されましたが、すぐにすべての公証役場で利用できるようになったわけではありません。デジタル化に対応できる設備や体制が整った公証役場から順次開始されています。
利用を希望する場合は、事前に最寄りの公証役場に確認し、デジタル対応が可能かどうかを確かめる必要があります。2025年11月現在、都市部の公証役場では多くがデジタル対応を開始していますが、地方ではまだ準備中の公証役場もあります。
本人確認の厳格化
デジタル化により、本人確認がより厳格になりました。マイナンバーカードを持っていない場合は、事前に取得する必要があります。また、顔認証技術による確認がうまくいかない場合、手続きが進まない可能性もあります。
マイナンバーカードの取得には一定の時間がかかるため、遺言作成を急いでいる場合は、早めに準備を始める必要があります。
安易な作成によるトラブルのリスク
オンラインで手軽に作成できるようになることで、十分な検討をせずに遺言を作成してしまう可能性があります。遺言の内容が不明確だったり、法的に問題があったりすると、相続時にトラブルを引き起こす恐れがあります。
特に、相続財産に不動産や非上場株式などが含まれる場合や、相続人が複数いる場合は、専門家に相談することが強く推奨されます。手軽に作成できるからこそ、内容については慎重に検討する必要があるのです。
公正証書遺言の費用について
公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。この手数料は、公証人手数料令という政令で法定されており、全国どこの公証役場でも同じ基準で計算されます。
費用の計算方法
公正証書遺言の手数料は、遺言で相続または遺贈を受ける人ごとに、その財産の価額を算出し、これを基準表に当てはめて計算します。各受遺者・相続人に対応する手数料額を合算して、遺言公正証書全体の手数料を算出します。
具体的には、目的の価額が100万円以下の場合は5,000円、100万円を超え200万円以下の場合は7,000円、200万円を超え500万円以下の場合は11,000円、500万円を超え1,000万円以下の場合は17,000円、1,000万円を超え3,000万円以下の場合は23,000円、3,000万円を超え5,000万円以下の場合は29,000円、5,000万円を超え1億円以下の場合は43,000円という基準になっています。
遺言加算の改定
全体の財産が1億円以下のときは、算出された手数料額に加算額が上乗せされます。これを「遺言加算」といいます。2025年10月の制度改正により、この遺言加算の額が1万1,000円から1万3,000円に改定されました。この改正は約20年ぶりの手数料改定となっています。
電子データでの交付費用
2025年10月のデジタル化に伴い、公正証書の正本・謄本を受け取る方法が複数用意されました。電子データでの提供を受ける場合は1通あたり2,500円、電子データを出力した書面(紙)での交付は1枚あたり300円となっています。
従来は紙での交付のみでしたが、デジタル化後は、メールでの受信(クラウド経由でのダウンロード)、自前のUSBメモリ等を使ってデータで受け取る、または紙で受け取る、という三つの方法から選択できます。
具体的な費用例
例えば、財産8,000万円を妻4,000万円、長男2,000万円、長女2,000万円に相続させる場合、妻への相続分(4,000万円)が29,000円、長男への相続分(2,000万円)が23,000円、長女への相続分(2,000万円)が23,000円、遺言加算(全体が1億円以下)が13,000円で、合計88,000円となります。
また、財産5,000万円を配偶者に全額相続させる場合は、配偶者への相続分(5,000万円)が29,000円、遺言加算(全体が1億円以下)が13,000円で、合計42,000円となります。
その他の費用
証人の日当として、証人を公証役場や専門家に依頼する場合、1人あたり5,000円から15,000円程度が必要です。知人に依頼する場合は無料のこともありますが、謝礼を渡すことが一般的です。
専門家への報酬として、弁護士、司法書士、行政書士などに遺言内容の相談や原案作成を依頼する場合、5万円から20万円程度の報酬が発生します。財産の規模や内容の複雑さによって異なります。
従来は、公証人が病院や自宅に出張する場合、別途出張費用(日当や交通費)が加算されていましたが、デジタル化後は、公証人の出張が不要になる場合が増えるため、この出張費用を節約できる可能性があります。
費用軽減制度
2025年10月の制度改正では、経済的に不安のある方の負担を軽減し、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者など、特に支援が必要な方が利用しやすいよう、一定の条件下で手数料が軽減される制度が設けられました。詳細は公証役場にお問い合わせください。
デジタル化による費用面での変化
デジタル化によって、公証人手数料の基本的な計算方法は変わりません。ただし、公証役場への交通費が不要になる、証人の交通費を節約できる、公証人の出張費用が不要になる場合がある、電子データでの受け取りを選べば紙の交付費用を抑えられる、といった費用面でのメリットがあります。
一方で、電子データの受け取りには2,500円の手数料がかかりますが、紙での交付でも複数枚になれば相応の費用がかかるため、大きな違いはありません。総合的に見ると、デジタル化により費用面での負担は軽減される傾向にあります。
相続時の手続き
遺言者が亡くなり、相続が発生した場合、相続人は公証役場で公正証書遺言の謄本を取得します。デジタル化後は、謄本を電子データで取得することも可能になりました。
電子データであれば、遠方の相続人でもオンラインで取得でき、相続手続きがスムーズに進みます。従来は、遠方に住んでいる相続人が謄本を取得するために、わざわざ公証役場に出向くか、郵送での手続きを待つ必要がありましたが、デジタル化後は、オンラインで迅速に取得できます。
公正証書遺言があれば、家庭裁判所での検認手続きは不要です。遺言の内容に従って、相続手続きを進めることができます。この点は従来と変わりませんが、電子データでの謄本取得により、相続手続き全体の迅速化が期待されています。
従来の方法も選択可能
デジタル化が開始されても、従来通り公証役場に出向いて、紙の書類で公正証書遺言を作成する方法も引き続き利用可能です。遺言者は、自分の状況や希望に応じて、オンライン方式と従来の方式のどちらかを自由に選択できます。
デジタル機器の操作に不安がある方や、直接公証人と対面で話したい方は、従来の方法を選ぶこともできます。デジタル化は選択肢を増やすものであり、強制されるものではありません。自分にとって最適な方法を選ぶことが大切です。
公正証書遺言と他の遺言方式の比較
日本の民法では、主に三つの遺言方式が認められています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。費用がかからず、いつでも作成できる手軽さがありますが、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクがあります。家庭裁判所での検認手続きが必要です。
ただし、2020年7月から法務局での遺言書保管制度が開始され、法務局に遺言を保管してもらうことで、紛失や改ざんのリスクを回避でき、検認も不要になりました。この制度により、自筆証書遺言の利便性も向上しています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言で、最も確実性が高い方式です。無効になるリスクが低く、原本が公証役場で保管されるため紛失の心配もありません。検認も不要です。ただし、公証人手数料がかかり、証人2人が必要です。今回のデジタル化の対象となっているのが、この公正証書遺言です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証人に証明してもらう方式です。ほとんど利用されていません。手続きが煩雑で、内容については公証人の関与がないため、法律的な問題が生じるリスクがあります。
よくある質問
デジタル化された公正証書遺言の法的効力
デジタル化された公正証書遺言も、従来の公正証書遺言と全く同じ法的効力があります。作成方法や保管方法が変わるだけで、遺言としての効力に違いはありません。
オンラインと従来の方法の選択
それぞれにメリットがあります。公証役場が遠い、外出が困難、時間を節約したいという方はオンラインが便利です。一方、デジタル機器の操作に不安がある、直接公証人と対面したいという方は従来の方法が適しています。自分の状況に合わせて選択してください。
マイナンバーカードの必要性
本人確認の主な方法としてマイナンバーカードが想定されていますが、運転免許証やパスポートなど、他の身分証明書でも対応できる場合があります。具体的な運用は公証役場によって異なる可能性があるため、事前に確認してください。
証人のオンライン参加
はい、証人もオンラインで立ち会うことができます。証人は遺言者と同じ場所にいる必要はなく、それぞれ別の場所から参加することも可能です。
電子データの正本の受け取り方法
メールやクラウドストレージを通じて受け取る方法が想定されています。紙の書類を希望する場合は、郵送または公証役場での受け取りも可能です。
遺言の変更や撤回
遺言はいつでも撤回や変更ができます。新しい遺言を作成すれば、前の遺言の内容と矛盾する部分は自動的に撤回されます。デジタル化後も、この点は変わりません。
専門家への相談の必要性
必須ではありませんが、相続財産が複雑な場合や、相続人が複数いてトラブルが予想される場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
今後の展望
公正証書遺言のデジタル化は、2025年10月から開始されましたが、今後さらなる進展も期待されています。
自筆証書遺言についても、デジタル化の検討が進められています。現在、自筆証書遺言は全文を自書する必要がありますが、将来的にはデジタル機器での作成が認められる可能性もあります。
また、遺言書保管制度とデジタル公正証書遺言の連携も期待されています。法務局での遺言書保管制度と公証役場でのデジタル遺言が連携すれば、相続手続きがさらにスムーズになる可能性があります。
デジタル化は、相続手続き全般の効率化にもつながります。不動産登記や銀行口座の名義変更など、相続に関わる様々な手続きがデジタル化されることで、相続人の負担が大幅に軽減されることが期待されます。
まとめ
2025年10月1日から施行された公正証書遺言の作成手続きのデジタル化は、日本の相続制度における大きな転換点となりました。オンラインでの面談、電子署名、電子データでの保管が可能になり、遺言作成のアクセシビリティが大きく向上しました。
特に、高齢者や身体が不自由な方、地方在住の方にとって、大きなメリットがあります。時間や費用の節約、安全な保管、手続きの簡素化なども実現しています。
一方で、デジタル機器への不慣れやインターネット環境の必要性、セキュリティリスクなど、注意すべき点もあります。すべての公証役場で対応しているわけではないため、事前の確認が必要です。
従来通りの方法も選択できるため、自分の状況に合わせて最適な方法を選ぶことができます。遺言は、自分の財産を希望通りに相続させるための重要な手段です。デジタル化により、より多くの人が遺言を作成しやすくなりました。
ただし、遺言の内容については、専門家に相談しながら慎重に検討することが大切です。手軽に作成できるようになったからこそ、内容についてはより慎重に、法律的な観点からも適切な検討を行うことが求められます。公正証書遺言のデジタル化は、相続の準備をより身近なものにする重要な制度改正であり、今後の相続手続きの在り方を大きく変えていく可能性を秘めています。
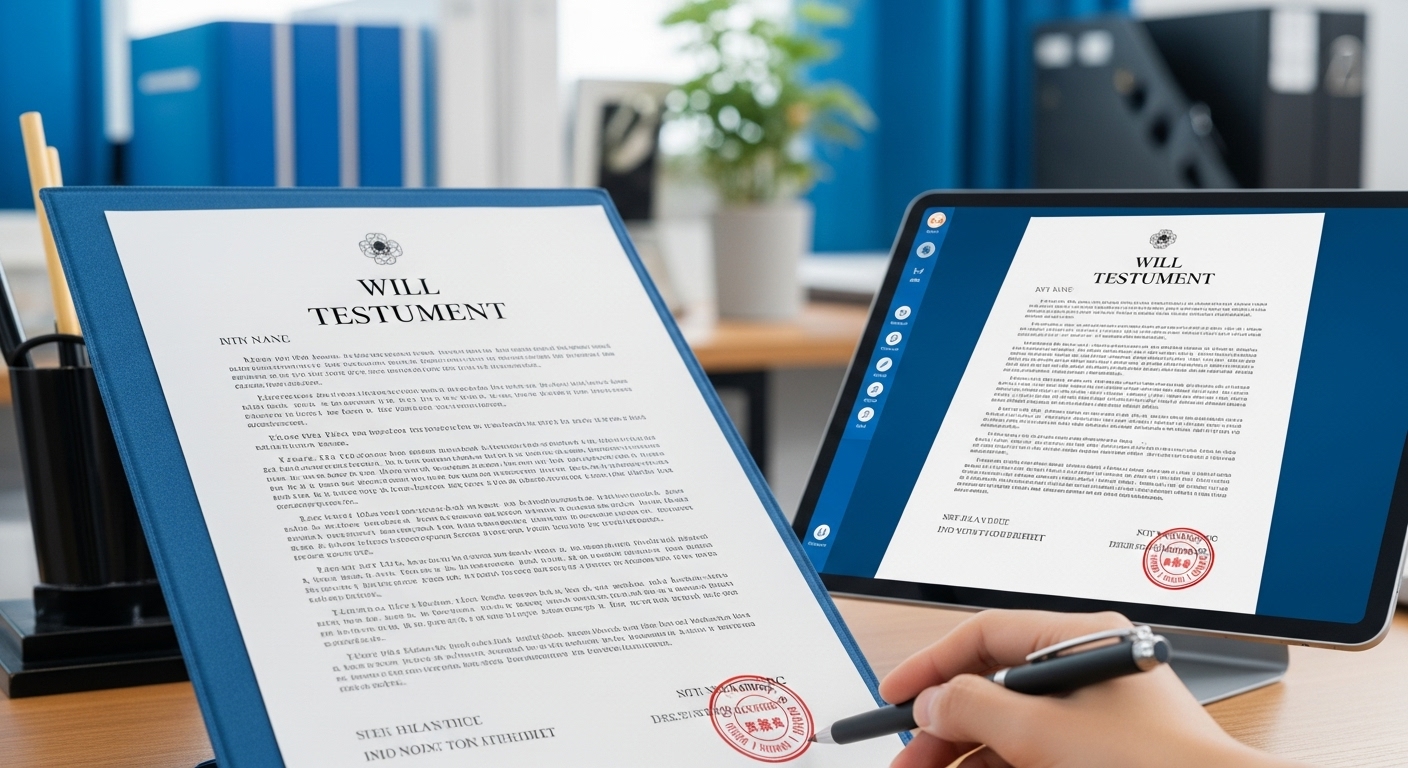








コメント